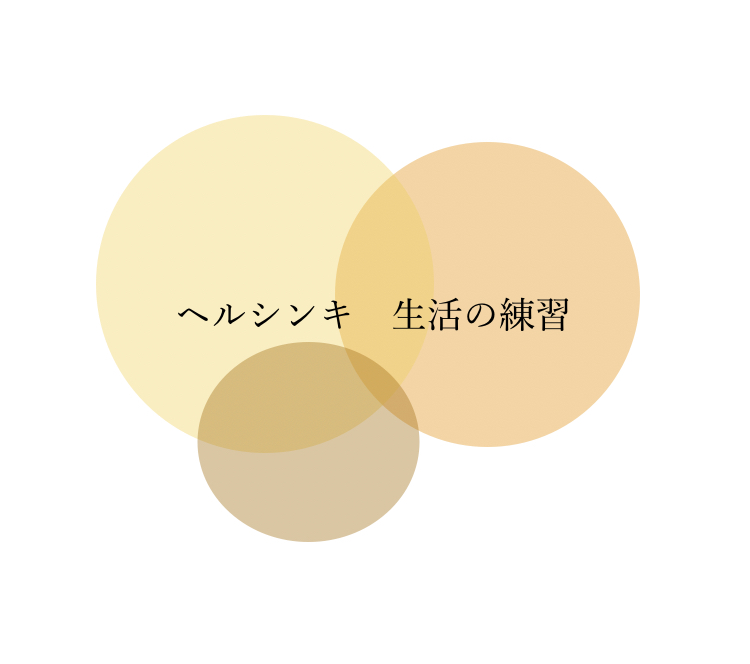北欧はヒュッゲな本を読んだばかりでイメージは幸福度の高い国。
しかし、この本を読んで北欧のイメージがかわりました。
ヒュッゲな暮らしからは想像できない北欧のリアルな部分。
作者の朴沙羅さんの書くヘルシンキでの子育て、仕事、お金事情など生々しい内容が赤裸々に描いてありました。
また、朴沙羅さんが思う日本との違い(優越ではない)は、日本しか知らない私にとって視野が広がる感じがしました。
偏った考えではなく、柔軟に世界を見てみなくては…。
さて、本日は贅沢バニラのカントリーマアムをお供に本を読み進めていきます。

在日コリアンが日本を飛び出した理由
朴沙羅さんは、お父様が韓国人お母様が日本人、京都生まれのハーフ在日だそうです。
幼少期から日本でのいじめ、差別を経験します。
この本を読んでいるとユーモアのセンスが抜群で知的な印象を受けた朴沙羅さんですが、日本の生活では思い悩むことも多かったようです。
そんな朴沙羅さんが、ヒュッゲな暮らしに憧れた?北欧ヘルシンキへと移住します。
なぜヘルシンキ?それはヘルシンキが干渉する人の少ない国だと感じたからだそうです。
朴沙羅さんが感じた日本での息苦しさは人間関係がつながりすぎてしまう点にあるのかもしれません。
続きが気になる方は

計画性のない日本からヘルシンキへの移住
ヘルシンキへは旅行で訪れたことがあった朴沙羅さん。
そこで感じたヘルシンキの雰囲気は、ヒュッゲな生活とは違うけれど、干渉してこないヘルシンキの人々は魅力的だったようです。
ヘルシンキ大学への再就職が決定と同時に子ども2人と旦那さんと一緒に、ヘルシンキへ。
(しゃべれないフィンランド語、小さな子どもを連れての移住、移住先でのコロナの影響などさまざまな試練が朴沙羅さんによって語られます)
ヘルシンキの教育とは 人を人格で判断しない
朴沙羅さんがヘルシンキで感じた教育は日本とは大きく異なるものだったようです。
See the Good.
というカードをこの本で始めて知りました。
人のスキルをカードにしたもので、子どもたちはこのカードを使って友達と遊びます。
このカードにはそれぞれのスキルは生まれもったものではなく、後天的に身につけることができる。
カードでは人を人格で判断しない、という意味が込められているようです。
また先生が子どもを褒めるときの視点が、その子のスキルを褒めるというものが基本だと書いてありました。
人柄がいいのも、協調性があるのも、すべてスキルとして後天的に身に着けることができる。
ヘルシンキで朴沙羅さんがみた、お互いに持っているスキルを確認し合う教育は、私も日々意識していきたい部分です。
子育てでの躓きで感じたソサエティ
朴沙羅さんがヘルシンキで生活を始めてから、世界ではさまざまな変化が訪れました。
異国の地で子育てをする中、コロナによる影響もあり朴沙羅さんの心身は次第にバランスを崩していったようです。
助けを求める場所として、テレホン相談を受けたとのこと。
そこで朴沙羅さん自身のソサエティを進められます。
思わぬ言葉に「???」と持った朴沙羅さんですが、この話は奥深いものでした。
人と人との交流は、”やりたいこと”の延長にありそこから人間関係が作られていく。
無理に人間関係だけを作るものではなく、子育て中でも、ママ友ではなく、一個人としての交流を作ることが大事なようです。
移住したからこそ得られた成長記録
生活の練習というタイトル通り、移住後の朴沙羅さんの生活を通して読者も一緒に生きることについて学ぶことができます。
読んでいて朴沙羅さんの言葉がリアルに感じとれて涙が止まらないことも。
大きく感情を動かされました。
正直、辛い生活の部分もありましたが、朴沙羅さんのユーモアで読み切ったのですが、読み終わると達成感がすごかったです。
素敵な本との出会いだと感じました。
みなさんも、よかったらこの感動を味わってみてください。